
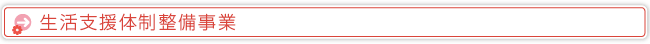

年齢を重ねてもいきいき暮らせるまちに
~生活支援体制整備事業~
現在、大網白里市では、およそ3人に1人が高齢者という状況であり、日常生活において、いろいろな手助けを必要としている方が増えてきています。
そのため、大網白里市及び大網白里市社会福祉協議会では、市民の皆様が住み慣れた地域で、安心して生活できる地域環境をつくるため、支え合い・助け合いの輪を広げていこうという取り組み(生活支援体制整備事業)を進めています。
市内の独居高齢者を対象に困りごとの実態を調査しました
市内にお住まいの高齢者の皆さんが、日々の生活を送る中で、どんなことに不便を感じているか、どういった手助けがあったら、暮らしやすくなるかなどを考えていく参考とするため、令和元年度に、ひとり暮らし高齢者の皆さんを訪問させていただき、聴き取り調査を行いました。
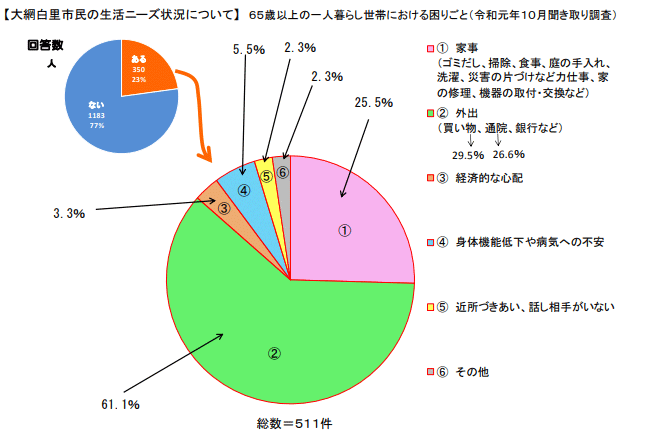 「こうなったらいいね」を話し合う場(協議体)が活動しています
「こうなったらいいね」を話し合う場(協議体)が活動しています
困りごとは、人によっても、地域の実情によっても様々です。そこで、地域の福祉活動に携わっている関係者が主体となり、支え合い・助け合いの仕組みづくりについて話し合う場(協議体)が発足しました。
この協議体が主体となり、地域の困りごとを解決するために、地域ならではの支援方法を考えていきます。
協議体には、次の2種類があります。
▼第1層協議体(大網白里市ささえあいのまちづくり会議)
市全域にわたる広域的な課題を協議します。
▼第2層協議体
市内5つの地域(瑞穂、山辺、大網、増穂、白里)ごとに、社会福祉協議会の支部が中心となって設置されました。地域の実情に合った支え合い・助け合いの仕組みづくりについて話し合っていきます。
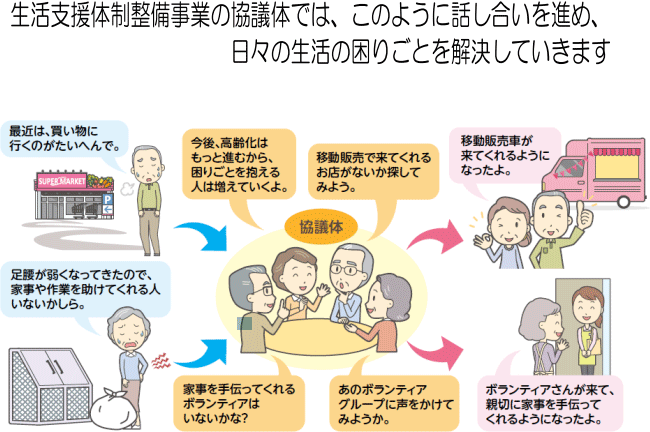
協議体の取り組みの紹介
【第 1 層協議体】
| 会議回数 |
開催日 |
議題等 |
会議結果等 |
| 第1回会議 |
平成28年
7月11日 |
- 国の方針及び市の計画について
- 大網白里市生活支援・介護予防体制整備推進協議体の設置について
- 大網白里市生活支援・介護予防体制整備事業業務委託について
- 地域資源及び地域ニーズの把握について
|
第1層協議体及び第2層協議体、生活支援コーディネーターの位置づけ・役割、ニーズと社会資源の概念などについて、市より説明がありました。
第 1 層協議体の名称を「ささえあいのまちづくり会議」とすることが承認されました。
|
| 第2回会議 |
令和2年
9月25日 |
- 大網白里市生活支援体制整備事業の推進体制について
- 令和元年度までの主な取り組み経過
- 令和2年度事業について
- 第2層協議体の活動状況について
- 意見交換
|
事業の基本的な推進体制について市より説明がありました。
担い手の育成、第2層協議体の発足経緯、高齢者の困りごと聴き取り調査の結果が報告されました。
令和2年度の主な取り組みとして、社会資源調査・社会資源マップの作成を計画していることの説明がありました。
|
| 第3回会議 |
令和2年
12月25日 |
- 前回会議以降の経過報告
- 社会資源のとりまとめ進捗状況
- 第2層協議体の活動状況について
- 意見交換
|
コーディネーター会議、協議体研修会を実施したことなどの報告がありました。
社会資源情報誌の配布対象、配布方法について意見交換しました。
広報紙等で十分周知しながら、区・自治会も含め関係者が協力し、配布していくことを確認しました。
各2層協議体より活動状況の報告がありました。
|
【第 2 層協議体】
月 1 回程度、委員が集まり会議を開催しています。
会議では、それぞれの地域ごとに、高齢者の皆様が不自由なく暮らせているか、また、生活上の困りごとで悩んでいる方がいないか、などについて情報交換したり、地域のなかで行われている支え合い活動や助け合い活動を高齢者の皆さんへ紹介したりする取り組みを推進しています。
主な取り組み
1.会議等
| 活動時期 |
議題等 |
会議結果等 |
令和2年6月
協議体会議の開催 |
- 生活支援体制整備事業の勉強会
- 今年度の事業計画
|
生活支援体制整備事業について、協議体構成員の理解が深まりました。
具体的な事業内容について、共通理解が図られました。
|
令和2年7月
協議体会議の開催 |
- 社会資源2次調査について
- 移動販売の地域拡大の取り組みについて
|
社会資源の1次調査で回答のあった事業所に対し、2次調査を実施していくことを確認しました。
買物困難者へ移動販売を普及する取り組みを推進していくことを確認しました。
|
令和2年
7月~9月 |
- 社会資源の調査を実施
|
地域内にある民間事業者のサービスやボランティア団体の活動のうち、高齢者の生活を支えるサービスをとりまとめていくため、調査活動を実施しました。
|
令和2年9月
協議体会議の開催 |
- 第2層協議体名称について
- 生活支援体制整備事業協議体研修会について
|
協議体に親しみやすい愛称をつけることについて協議しました。
先進事例の取り組みを学ぶため、10 月 19 日に協議体委員を対象とした研修会を計画し、参加者を募りました。 |
令和3年1月
協議体会議の開催 |
- 社会資源情報誌の配布方法について
|
冊子が完成した後、区・自治会や民生委員とも協力し、高齢者世帯へ配布していくことを確認しました。 |
2.買い物困難者への支援の取り組み
昨年の一人暮らし高齢者世帯への困りごと調査において、最もニーズが高かった買い物困難者への支援策として、第2層協議体が中心となって、移動販売の普及拡大を推進しています。
区・自治会や民生委員の皆さんの協力を得て、市民への周知を行い、買い物に困っている方の情報を収集しました。その結果をもとに、NPO法人が運営する移動販売車を利用できるよう、新たな巡回コースを設定したりしながら利用の促進を図った結、現時点で、市内全域で、5コース100人以上の方が利用するまで普及が進んでいます。
利用者からは、「新鮮な品物を直接見て買うことが出来てうれしい」「雨の日や寒い中を買い物に行かなくて済む」「歩いて重い荷物を持って帰らなくてよいので助かる」など、数多くの感謝の声が寄せられています。


移動販売車でお目当ての買い物をする利用者の皆さん
先進地である香取市社会福祉協議会の方々を講師として迎え、香取市における生活支援体制整備事業の取り組み状況について、説明をいただきました。
開催日 令和2年10月19日
内 容 香取市の取り組み状況の紹介
参加者 第1層協議体委員及び第2層協議体委員
市及び市社協職員
研修内容
①生活支援体制整備事業における現状の推進体制と課題対応
②「ささえあい香取」香取地区買い物・通院支援の取り組み
③「ささえあい香西」大崎えがおサロンお助けサービスの取り組み
香取市の人口は、現在約72,000人、高齢化率36%ということで、大網白里市より若干高齢化が進んでいます。
平成27年7月に生活支援体制整備事業の研究会を立ち上げ、平成28年10月第1層協議体が発足。平成30年5月には、最初の第2層協議体が発足し、その後、他の地区も順次発足し、現在14地区が活動中です。
委員には、地域の福祉関係者だけではなく、介護事業所や薬局など民間事業所の方々も参画しているということで、多様な視点で考えたり協力しあったりできることが良い点だということです。
また、第2層協議体が中心となって、新たな助け合いのサービス創出にも取り組んでおり、「買い物・通院支援」や「毎週開催するサロン」を実施しています。サロンはとても好評で、参加者の皆さんは当日が待ち遠しいと楽しみにしており、体操などのレクリエーションを通して体力が向上して元気になり、徐々に効果が表れてきているということです。
今後の本市の取り組みを進めるうえで、たいへん参考となるお話しを伺うことができました。
4.高齢者お役立ち情報誌【こすもす手帳】の作成
高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにという趣旨で、市内の民間事業者やボランティア団体などの皆様からお寄せいただきました貴重な情報をもとに、日々の生活に役立つ便利なサービスをとりまとめ、「こすもす手帳」として作成しました。
高齢者の皆さんが、日頃の生活を送るうえで、「こんなことがあったらもっと暮らしやすくなるね」という思いに応えるため、地域の支えあいや助けあいを推進しようと、生活支援体制整備事業の一環として、「大網白里市ささえあいのまちづくり会議(第1層協議体)」及び「各地域のささえあい会議(第2層協議体)」での話し合いを重ねながら編集しました。
家事や外出が難しくなった高齢者の皆様が、自宅に居ながら受けられる、思いやりのサービスが豊富に掲載されています。
 掲載されている主な内容
掲載されている主な内容
弁当や食料品の配達・移動販売、日用品・灯油の配達、買い物送迎・外出支援、家事支援・生活支援、理美容・クリーニング集配、自転車や自動車の修理、趣味・健康づくり・居場所、見守りサービス、医療機関の情報、公共のサービス・相談窓口 など
こすもす手帳は、3月以降に、65歳以上のお一人住まいの方及びご家族全員が75歳以上のご家庭にお配りしています。
これ以外の方で、ご希望される場合は、市内の各公共施設に備えてありますので、お持ちください。
また、ホームページでもPDFファイルでご覧いただけます。
ご不明な点などありましたら、お問合せください。
 令和3年度の取り組み
令和3年度の取り組み
 令和4年度の取り組み
令和4年度の取り組み
 令和5年度ささえあいのまちづくり通信10月号
令和5年度ささえあいのまちづくり通信10月号
 令和5年度の取り組み
令和5年度の取り組み
 令和6年度ささえあいのまちづくり通信10月号
令和6年度ささえあいのまちづくり通信10月号
 令和6年度の取り組み
令和6年度の取り組み

